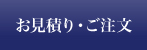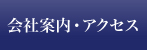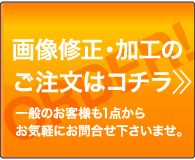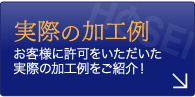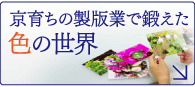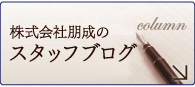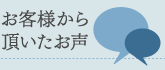-
京都・龍安寺の「つくばい」
- 12.01.30 カテゴリー:コラム
-
さて、この“つくばい”は水戸黄門が、龍安寺から本を借りたお礼に
寄進したもの。
さすがは越後のチリメン問屋を名乗るだけあって、粋なデザインです。
実はこちらはレプリカで、本物は茶室前にあって非公開。
一般的によく見る“つくばい”は、コーン!と日本情緒たっぷりに響く
獅子落としの音を受ける部分は丸。
しかし、こちらは四角で口の形にして、それを囲むように『吾唯足知』の
文字を造形しています。(よく見えないけど上から時計廻りで)
この四文字熟語みたいな言葉は、お釈迦様の遺言とも言われる『遺教経』の
中に書かれている知足の心。

【知足の者は賤しとも雖も富めり 不知足の者は富めりと雖も賤し】と、
あるところから取ったそうな…字、読めません。
また、孔子の言葉には【足ることを知る者は心安らかなり】と、教えています。孔子の言葉だと、かなりの理解力アップで、シミジミと心に染み入るお言葉です。

(引用)
つくばいとは茶室に入る前に手を清めるために置かれた背の低い手の低い手水鉢
に役石をおいて趣を加えたもの手水で手を洗うとき「つくばう(しゃがむ)」
ことからその名があるそうです。写真の修正・加工・
高解像度スキャニングの事なら
一般のお客様も、1点からでも
お気軽にお問合せ下さいませ。
(*勿論、お見積りは無料です。)